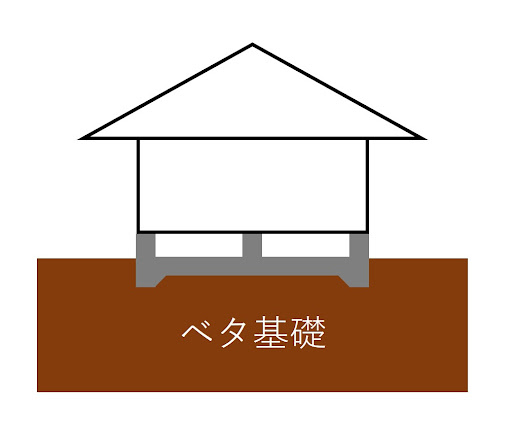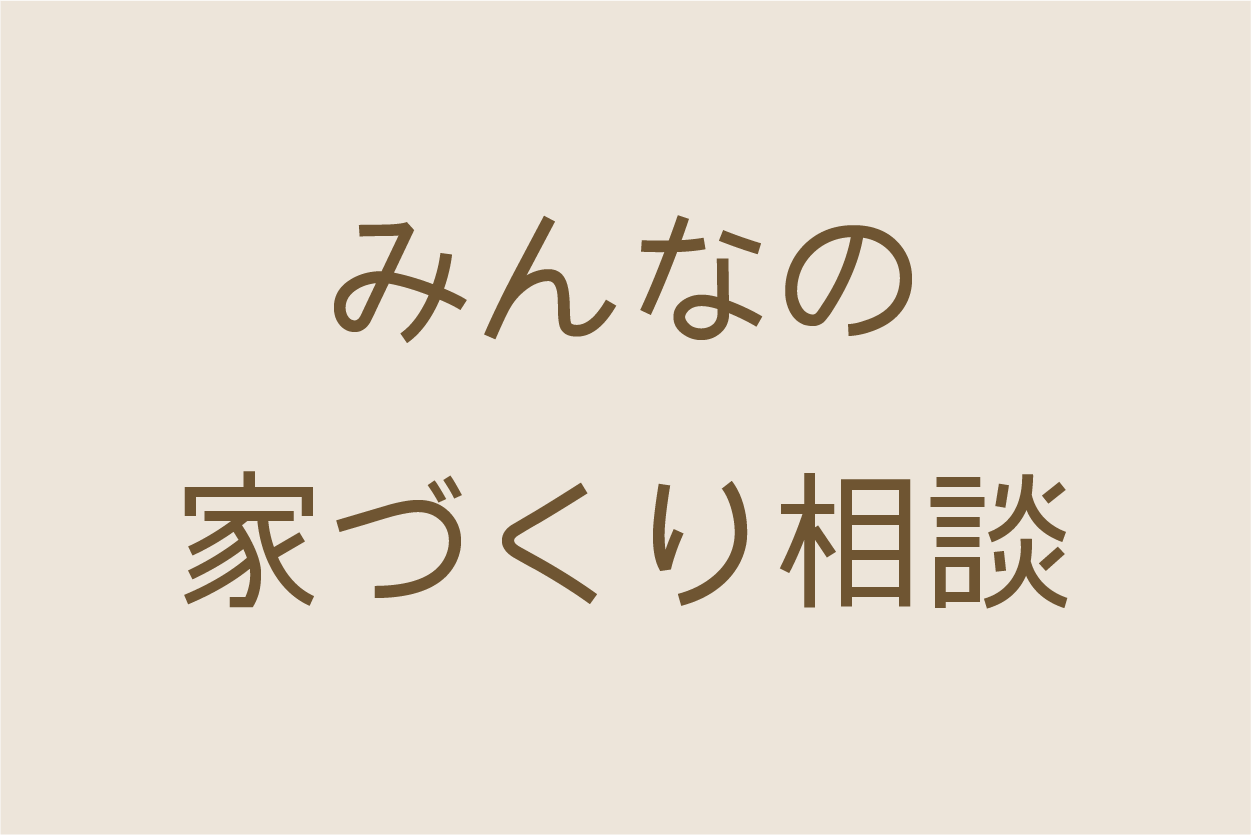家財保険は100万円で十分?保険金額の決め方やポイントを解説
「家財保険って、実際にはいくら必要なのか知りたい」
「家財保険は100万円あれば足りる?」
このような悩みを抱えていませんか?
万が一の際に頼りになる保険ですが、その中でも家財保険についてくわしく知っている方は少ないのではないでしょうか。
この記事では、家財の損害に備える家財保険の概要や2つの算定方法、金額を決めるときのポイント3つについて解説します。
読んでいただくことで、損をしない家財保険料の決め方がわかります。ぜひ最後まで読んでみてください。
家財保険は100万円で足りるのか

災害などによる家財の損害を補償する家財保険は、100万円あれば足りるのでしょうか。ここでは家財保険の概要や、最低いくら必要になるのかについて解説します。
家財保険の金額は任意
まず確認しておきたいのが、家財保険の金額は任意で決められる点です。契約者本人が、家財の量などに応じて金額を設定できるため、自由度の高い保険といえるでしょう。
一方で、金額を十分に検討しないと高い保険料を不必要に払い続けることになります。
このことから、家財保険の内容をしっかり理解して自分にあった金額を設定することが重要です。
最低補償額に注意が必要
家財保険には、保険会社によって「最低補償額」が定められています。最低補償額とは、最も安い保険料で契約したときに補償される金額のことです。つまり、保険会社としては「家財の損害として、この金額は最低でも必要になるだろう」と設定している金額といえます。
この最低補償額を300万円に設定している保険会社もあるため、100万円の補償額で契約したいと考えても契約できません。
このようなことから、一般的に家財保険は100万円では足りないと考えたほうがよいでしょう。
家財保険は最低いくら必要か
それでは、家財保険は最低いくら必要なのでしょうか。
最低補償額を300万円に設定している保険会社があるため、300万円という額も1つのラインといえるでしょう。しかし、世帯構成や家財量によっても最低限必要な金額は変わってきます。
たとえば一人暮らしであれば300万円、夫婦2人世帯の場合には500万円前後必要と言われています。また夫婦世帯に子どもが1人加わると最低600万円は必要と言われており、家財量が多い場合には必要な金額は増えるでしょう。
このように最低でも300万円前後が必要で、世帯人数の増加や家財量の多さによって必要な金額は増えていきます。
家財保険金額の算定方法2つ

家財保険の金額を算定する方法には以下の2つがあります。
- ・積算評価法
- ・簡易評価法
それぞれくわしく見ていきましょう。
1.持っているものの金額を積み上げる(積算評価法)
1つめの方法は「積算評価法」で、持っているものの金額を積み上げて計算する方法です。
具体的には、家財の量を把握し、その家財をすべてもう一度購入すると仮定した場合に必要となる金額を算定します。これにより、万が一のときに必要になる保険金額を求めるという方法です。
ただし、家財保険の対象にならない家財があることには注意しましょう。また、1つあたり30万円を超える家財は「明記物件」として、保険証券に明記していないと補償を受けられないこともあるため、事前の確認が大切です。
所有している家財を、再調達するときに必要になる金額をもとに算出するこの方法では、実態に即した保険金額が求められます。その一方で、家財1つ1つの金額を丁寧に積み上げていく作業が必要になるため、時間のかかる手法といえるでしょう。
2.世帯構成や家の面積による金額の目安を参考にする(簡易評価法)
2つめの方法は「簡易評価法」で、世帯構成や家の面積などの基準をもとに金額を算定する方法です。
金額の基準としては、世帯構成や家の面積のほか、世帯員の年齢や人数、賃貸か持ち家か、集合住宅か戸建てか、などが挙げられます。
積算評価法に比べると、実態と多少ズレが生じる場合もありますが、算定が比較的簡単に行えることが強みでしょう。保険会社でも用いられる手法です。
ただし簡易評価法で用いる基準は、法律などで一律の基準が定められたものではなく、保険会社ごとに異なる点には注意しましょう。
家財保険料を決めるときのポイント3つ

家財保険の金額及び、その金額の補償を受けるために必要な保険料について、決めるときのポイントは以下の3つです。
- 1.家財の量や金額を把握する
- 2.保険金額の目安も参考にする
- 3.保険でどこまでカバーするか決める
それぞれくわしく見ていきましょう。
1.家財の量や金額を把握する
まず、家財の量や金額を把握しましょう。
あらためて把握してみると、想像以上に家財が多かったり、思っていたよりも少なかったりします。場合によっては、家財の整理を行うことで、必要な保険金額を抑えることができるでしょう。
また、再調達した場合の金額を算出することで、実際に必要になる金額がはっきりします。
このように、家財量や金額を把握することで、余計な保険料を支払うリスクを避けられるでしょう。
2.保険金額の目安も参考にする
保険金額の目安を参考にするのもおすすめです。
保険会社も使う簡易評価法に、世帯構成など自分の状況を当てはめることで、どれくらいの保険金額が相場なのかを確認できます。
相場と実情を照らし合わせながら、保険金額は多いほうがよいのか、少なくても大丈夫なのか、より細かい検討が可能になるでしょう。
3.保険でどこまでカバーするか決める
家財保険でどこまでカバーするのか決めることも、大切なポイントです。
たとえば、家財保険ですべてカバーするのではなく、預貯金から一部賄える場合もあるでしょう。そのような場合には、保険金額は安く済み、支払う保険料も抑えられます。
万が一の際に、どの部分を保険でカバーすればよいか十分に考えて、保険金額を決めるようにしましょう。
まとめ:家財保険で必要な金額はそれぞれ異なる | 家財量や必要な補償を踏まえて金額を決めよう
この記事では、家財の損害に備える家財保険の概要や2つの算定方法、金額を決めるときのポイント3つについて解説しました。
家財保険で必要になる金額は、世帯構成や家財量のほか、貯金額などの要素も絡んで決まるため、人それぞれ異なります。このため、自分の状況に応じた適切な金額設定が重要です。
万が一のときに金額が少なすぎる、多すぎることがないよう、家財の見直しや保険会社の資料を比較するなどして、自分に合った保険や保険金額を見つけましょう。